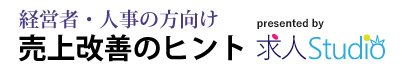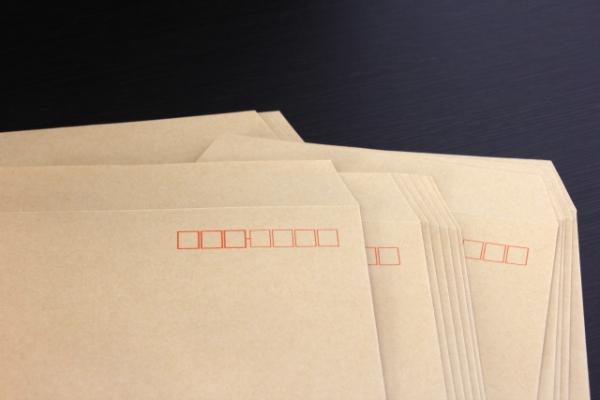【人事・経営者向け】求人採用で自社のアピールばかりして応募者の気持ちを忘れていませんか?
※当サイトの記事は、プロモーションを含む場合があります。

この記事では、自社のWebサイト上での採用情報やハローワーク、求人サイト等で応募を増やす方法として
「自社のイメージアップや実績のアピールばかりに目を向けてばかりいるのでなく、応募者の気持ちになってみましょう。」というテーマで書かせていただきます。
世の中の求人情報をくまなく見渡していると、「自社がいかに優れているか」「いかに我が社がハイスペックな企業で業界をリードしているか」「先進的なテクノロジーの活用で遣り甲斐がある企業」等を掲げている企業が多いのですが、それを強調することだけにとらわれていると、応募者の気持ちとすれ違いが起きてしまうことがあります。
というのも、求職者側からすれば、「それはわかったけど、自分はそこでやっていけるスキルがあるのか?」「凄い企業なのはわかるけど、この企業の求めている仕事内容に自分は応えられるのか?」といった問いに対して答えていない場合が少なくないからです。
たとえ立派なスキルがある人であっても、自分がこの会社の要求に応えられるか、というテーマは大きな課題といえましょう。
とくに専門分野になればなるほど、さらに細分化された専門の分野、そしてさらに細分化された分野と、枝分かれしてゆく構造になることが良くあります。そこでスキルを磨いてきた人にとって、具体的な必須スキルを細分化して把握できることはとても重要です。
すなわち、求職者は「それだけのレベルの高い企業」であれば、そのレベルの丈に見合った「自分のスキルでも大丈夫なのか?」という両天秤の狭間で心が揺れ動くことがあるのです。
東京労働局に直接確認したところ、募集要項に「必須スキル」と「歓迎するスキル」を書くことは男女差別、年齢制限等の法に抵触しない限り求人募集要項に記載することは問題ありません。
他の求人系サイトで「歓迎するスキルの掲載は差別に該当するので法的にNG」と指摘しているサイトもありますが、その内容は東京労働局に確認して間違いであることが判明しています。
というのも、ハローワークで既に掲載されているというご指摘です。なるほど、と筆者は思いました。
採用条件の項目に記入する際は、「〇〇」のスキルがあれば歓迎する、あるいは採用条件として問題ないことを具体的にアピールしましょう。
一般の求人情報媒体の採用条件、応募条件等の項目だけでは、細かなニュアンスを伝えきれないことが多々あるかと思います。
そこで、おすすめするのがインタビュー機能の活用です。もし、自社の採用情報にインタビュー記事が無ければこれを期に追加することをお勧め致します。
また、求人サイトとしてインタビュー機能があれば、できるだけ活用しましょう。ちなみに、当サイトの求人Studioではインタビュー機能を無料にてご提供しております。
先に書きました通り、求人媒体の「採用条件」の項目だけでは、大まかな基準が提示されるだけで、細かなニュアンスを伝えられません。
というのも、「採用条件」という項目であれば、いかにも堅苦しい、形式ばった印象にならざるを得ないからです。
「採用条件」という項目は、客観的に書くことを求められ、厚生労働省、東京労働局からも「あいまいな条件」「主観的な条件」は提示しないように指導されているからです。
たとえば、NG表記としては、「やる気のある方」「簿記に熱意のある方」等です。ときどき、自社ウェブサイト等でこのような表記をしている求人の企業を見受けますが、この表現は労働局からの指導が入ってもおかしくない書き方ですので真似しないようにしましょう。
ただし、応募資格としてはあいまいな表現は禁止されているものの、働いている社員が自分の会社を語ることまでは禁止されていません。
そこで、インタビュー機能を活用して以下のような内容を書くと応募者に対して「この仕事は自分にもできるかもしれない」と思わせることができます。
「私は入社時に〇〇と△△のスキルしかありませんでしたが、この会社は先輩の手助けがとても充実しているお陰で私でも開発責任者になることができました。」
「個人的に思うことは、入社後は教育システムが充実しているので、〇〇と同程度の知識があれば仕事に適応できるかと思います。」
ここで重要なのは具体性です。ただ単に「やる気のある人」とか「教育に力を入れています」だけだと具体性に乏しいので説得性に欠けます。
具体的な必須レベルをさりげなく提示することで、「自分にもできる」と思わせることができるのです。
次に、業界別に具体例を出してみます。
このように書けば、Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQLite、DB2をやっていた人が対象になりますので、幅広くアプローチすることができます。
このように、ハードルを下げるだけでなく、ハイスペックな人が入社していることをあわせて掲載することで、レベルが高い人も入社しているという安心感を抱かせることもできます。
このように、具体的にブランク〇年で入社実績があるという例を示しておけば、例えば2年間のブランクの求職者の方が「このお店なら自分でも採用してもらえる」と思ってもらう可能性が出てくると思われます。
テレアポの場合、法人相手であれば、相手が紳士的に対応してくれることがほとんどである旨を実体験を交えながら書けば、応募者の方にとってエントリーへのハードルが下がります。
また、営業という職業でまたとない経験を積むことができる、という求職者の方のスキル磨きとしての将来性をアピールすることも有効的な方法かと思います。
このように書けば、「イラストレータを使ったことはあるが、グラデーションメッシュの使い方がよくわからない」という人でも応募しやすくなります。
採用条件に満たない人が増えれば無駄な採用お見送りの連絡をしなくてはなりません。
そのため、いたずらにハードルを下げるのではなく、「ここまでのスキル・キャリアがあれば十分。ただし、これ以下のスキルであれば不十分」とする線引きをしっかり明示することが大切かと思われます。
何はともあれ、具体的な情報を提供することで、応募者の方に正しく判断してもらうことがベストかと思います。
この記事の内容が良かったと思われた方はシェアを宜しくお願い致します!
「自社のイメージアップや実績のアピールばかりに目を向けてばかりいるのでなく、応募者の気持ちになってみましょう。」というテーマで書かせていただきます。
求人募集をする際に、いかに「業界内で優良企業」であるかをアピールすることにとらわれていませんか?
世の中の求人情報をくまなく見渡していると、「自社がいかに優れているか」「いかに我が社がハイスペックな企業で業界をリードしているか」「先進的なテクノロジーの活用で遣り甲斐がある企業」等を掲げている企業が多いのですが、それを強調することだけにとらわれていると、応募者の気持ちとすれ違いが起きてしまうことがあります。
というのも、求職者側からすれば、「それはわかったけど、自分はそこでやっていけるスキルがあるのか?」「凄い企業なのはわかるけど、この企業の求めている仕事内容に自分は応えられるのか?」といった問いに対して答えていない場合が少なくないからです。
たとえ立派なスキルがある人であっても、自分がこの会社の要求に応えられるか、というテーマは大きな課題といえましょう。
とくに専門分野になればなるほど、さらに細分化された専門の分野、そしてさらに細分化された分野と、枝分かれしてゆく構造になることが良くあります。そこでスキルを磨いてきた人にとって、具体的な必須スキルを細分化して把握できることはとても重要です。
すなわち、求職者は「それだけのレベルの高い企業」であれば、そのレベルの丈に見合った「自分のスキルでも大丈夫なのか?」という両天秤の狭間で心が揺れ動くことがあるのです。
募集要項では、〇〇のスキルの方は歓迎します。と具体的に書くことをおすすめします。
東京労働局に直接確認したところ、募集要項に「必須スキル」と「歓迎するスキル」を書くことは男女差別、年齢制限等の法に抵触しない限り求人募集要項に記載することは問題ありません。
他の求人系サイトで「歓迎するスキルの掲載は差別に該当するので法的にNG」と指摘しているサイトもありますが、その内容は東京労働局に確認して間違いであることが判明しています。
というのも、ハローワークで既に掲載されているというご指摘です。なるほど、と筆者は思いました。
採用条件の項目に記入する際は、「〇〇」のスキルがあれば歓迎する、あるいは採用条件として問題ないことを具体的にアピールしましょう。
インタビュー記事を活用すれば、さらに求職者の方にとって応募へのハードルが下がります。
一般の求人情報媒体の採用条件、応募条件等の項目だけでは、細かなニュアンスを伝えきれないことが多々あるかと思います。
そこで、おすすめするのがインタビュー機能の活用です。もし、自社の採用情報にインタビュー記事が無ければこれを期に追加することをお勧め致します。
また、求人サイトとしてインタビュー機能があれば、できるだけ活用しましょう。ちなみに、当サイトの求人Studioではインタビュー機能を無料にてご提供しております。
インタビュー記事を掲載できる媒体の場合は主観的に書けるので、「あなたのスキルでも大丈夫」であることをアピールすることができます。
先に書きました通り、求人媒体の「採用条件」の項目だけでは、大まかな基準が提示されるだけで、細かなニュアンスを伝えられません。
というのも、「採用条件」という項目であれば、いかにも堅苦しい、形式ばった印象にならざるを得ないからです。
「採用条件」という項目は、客観的に書くことを求められ、厚生労働省、東京労働局からも「あいまいな条件」「主観的な条件」は提示しないように指導されているからです。
たとえば、NG表記としては、「やる気のある方」「簿記に熱意のある方」等です。ときどき、自社ウェブサイト等でこのような表記をしている求人の企業を見受けますが、この表現は労働局からの指導が入ってもおかしくない書き方ですので真似しないようにしましょう。
ただし、応募資格としてはあいまいな表現は禁止されているものの、働いている社員が自分の会社を語ることまでは禁止されていません。
そこで、インタビュー機能を活用して以下のような内容を書くと応募者に対して「この仕事は自分にもできるかもしれない」と思わせることができます。
「私は入社時に〇〇と△△のスキルしかありませんでしたが、この会社は先輩の手助けがとても充実しているお陰で私でも開発責任者になることができました。」
「個人的に思うことは、入社後は教育システムが充実しているので、〇〇と同程度の知識があれば仕事に適応できるかと思います。」
ここで重要なのは具体性です。ただ単に「やる気のある人」とか「教育に力を入れています」だけだと具体性に乏しいので説得性に欠けます。
具体的な必須レベルをさりげなく提示することで、「自分にもできる」と思わせることができるのです。
次に、業界別に具体例を出してみます。
[Q] 入社するにはどのようなスキルが必要ですか?
とのインタビューの質問に対しての答えを以下に例として挙げてみます。IT業界のインタビュー掲載例
[A] Java、PHP、Perlのプログラムの仕事を2年以上経験があり、データベースの基本的なSQLの命令が理解できれば、あとはなんとかやっていけると思います。たとえば、select文やupdate文を実際に使ったことがあり、理解できる程度で十分OKです。
データベースを設計したことがある経験はOracle、MySQL、PostgreSQL、SQLite、DB2どれでもかまいません。基礎力さえあれば、研修で身に付けることが十分可能なレベルです。
データベースを設計したことがある経験はOracle、MySQL、PostgreSQL、SQLite、DB2どれでもかまいません。基礎力さえあれば、研修で身に付けることが十分可能なレベルです。
このように書けば、Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQLite、DB2をやっていた人が対象になりますので、幅広くアプローチすることができます。
[A] レスポンシブWEBデザイン、HTML5、CSS3のいづれかを構築した経験があれば十分かと思います。Javascriptは入社時に詳しくなくても入社後に自然と身につくようになります。
プログラミングの知識がほとんど無くて入社した人は多いですね。当社の技術部の社員の中には入社時に業界未経験者でワードプレスを趣味で運営した経験しかなかった人も何人かいます。
もちろん、プログラミング系の雑誌に多数寄稿したことがある凄腕のスキルで入ってきた人もいますので、入社時のレベルはピンキリといったところです。
プログラミングの知識がほとんど無くて入社した人は多いですね。当社の技術部の社員の中には入社時に業界未経験者でワードプレスを趣味で運営した経験しかなかった人も何人かいます。
もちろん、プログラミング系の雑誌に多数寄稿したことがある凄腕のスキルで入ってきた人もいますので、入社時のレベルはピンキリといったところです。
このように、ハードルを下げるだけでなく、ハイスペックな人が入社していることをあわせて掲載することで、レベルが高い人も入社しているという安心感を抱かせることもできます。
美容業界のインタビュー掲載例
[A] 美容師また理容師免許がある方で、1年以上のヘアカットの経験があれば問題ありません。シャンプーやリンスはオーガニックの成分を使っていますので手が荒れずに済みます。
ブランク等があっても研修でカバーできますので、相談してみてください。過去に出産等で5年以上のブランクがあって採用された人もいます。
ブランク等があっても研修でカバーできますので、相談してみてください。過去に出産等で5年以上のブランクがあって採用された人もいます。
このように、具体的にブランク〇年で入社実績があるという例を示しておけば、例えば2年間のブランクの求職者の方が「このお店なら自分でも採用してもらえる」と思ってもらう可能性が出てくると思われます。
営業(テレアポ)の場合のインタビュー掲載例
[A] 営業経験が1年以上ある方であれば業界は問いません。当社では入社時でのテレアポ未経験の人が7割近くいますが、めきめき実力を伸ばしています。
当社は法人相手ですので、個人向けと違い、今までの経験上電話して電話口で怒鳴られたという経験はほとんどありませんので初めての方でも落ち着いて電話することができます。
当社は法人相手ですので、個人向けと違い、今までの経験上電話して電話口で怒鳴られたという経験はほとんどありませんので初めての方でも落ち着いて電話することができます。
テレアポの場合、法人相手であれば、相手が紳士的に対応してくれることがほとんどである旨を実体験を交えながら書けば、応募者の方にとってエントリーへのハードルが下がります。
また、営業という職業でまたとない経験を積むことができる、という求職者の方のスキル磨きとしての将来性をアピールすることも有効的な方法かと思います。
アパレル業界のデザイナーインタビュー掲載例
[A] 当社ではデザイナー未経験の方でも問題なくアパレルデザインの仕事をすることができます。
仕事ではフォトショップやイラストレータを使うことが日常です。とくにイラストレータを使った経験は必須です。
ただし、入社時点ではペンツールや透明マスクを普通に使える程度であれば、その後に研修がありますので十分やってけると思います。グラデーションメッシュ、ベジェ曲線等の使い方がよくわからない方でも採用条件としては問題ないと思います。
仕事ではフォトショップやイラストレータを使うことが日常です。とくにイラストレータを使った経験は必須です。
ただし、入社時点ではペンツールや透明マスクを普通に使える程度であれば、その後に研修がありますので十分やってけると思います。グラデーションメッシュ、ベジェ曲線等の使い方がよくわからない方でも採用条件としては問題ないと思います。
このように書けば、「イラストレータを使ったことはあるが、グラデーションメッシュの使い方がよくわからない」という人でも応募しやすくなります。
応募のハードルを下げることでの注意点
応募のハードルを下げれば、たしかにエントリーしてくる人は増えますが、それと同時に採用条件に満たない人も増える可能性があります。採用条件に満たない人が増えれば無駄な採用お見送りの連絡をしなくてはなりません。
そのため、いたずらにハードルを下げるのではなく、「ここまでのスキル・キャリアがあれば十分。ただし、これ以下のスキルであれば不十分」とする線引きをしっかり明示することが大切かと思われます。
何はともあれ、具体的な情報を提供することで、応募者の方に正しく判断してもらうことがベストかと思います。
人材採用 カテゴリ記事
Copyright (C) 2018 経営者・人事の方向け 売上改善のヒント by 求人Studio All Rights Reserved.
※当サイトの内容の無断転載を固く禁じます。
※当サイトの内容の無断転載を固く禁じます。